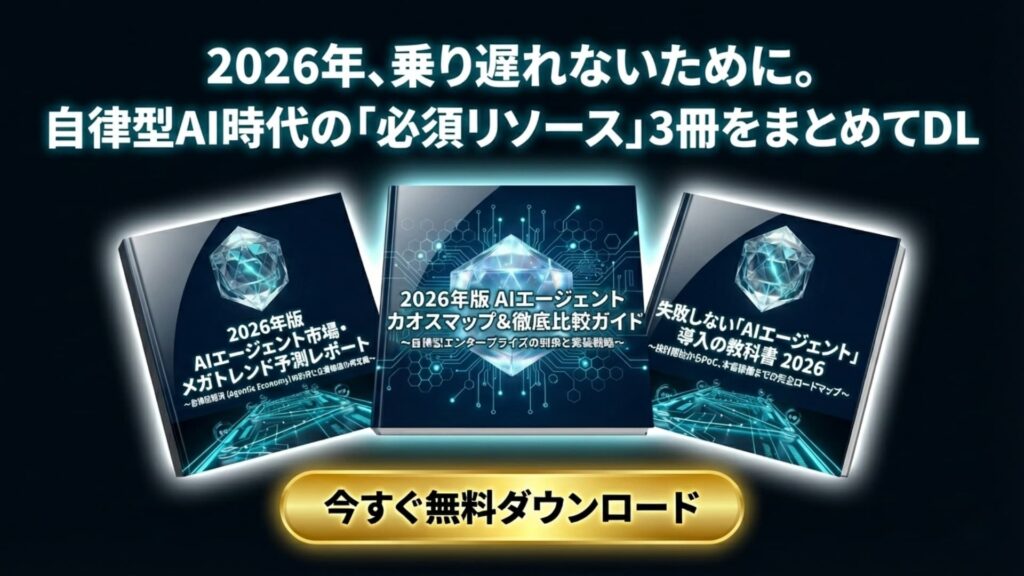【生成AIと法律】企業が知るべき著作権・個人情報保護法を解説
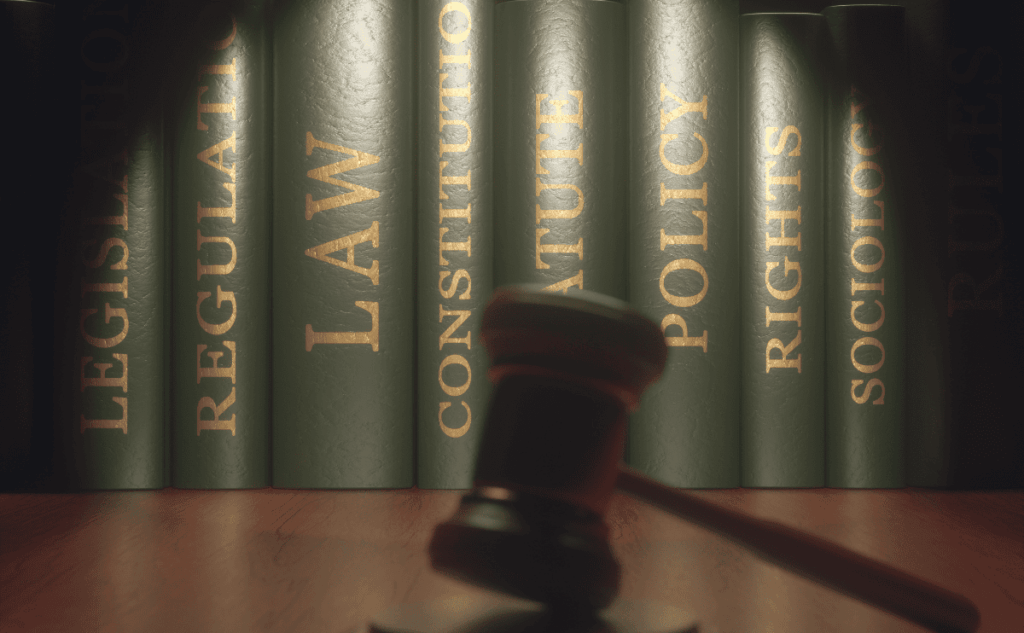
生成AIのビジネス活用を成功させる鍵は、その利便性だけでなく、関連する「法律」のリスクを正しく理解し、管理することにあります。
特に「著作権法」と「個人情報保護法」は、従業員による安易な利用が意図せぬ法律違反に繋がり、企業に深刻なダメージを与えかねない重要分野です。
本記事では、企業の法務・コンプライアンス担当者、そして事業責任者が知っておくべき生成AIと法律の問題について、主要な論点と実践的な対策を分かりやすく解説します。
目次
なぜ今、生成AIの「法律」問題が重要なのか?
生成AIの普及により、誰もが手軽に高度なコンテンツを作成できるようになった一方で、そのプロセスにおける法的リスクも顕在化しています。企業にとって、生成AIに関する法務対応は、もはや「他人事」ではなく、事業継続に関わる経営課題となっています。
1. 意図せぬ「権利侵害」のリスク
従業員が悪意なく生成AIを利用した結果、他者の著作権や個人情報を侵害してしまうリスクが高まっています。例えば、AIが生成した画像が既存のキャラクターに酷似していたり、顧客情報をプロンプトに入力してしまったりするケースです。これらの行為は、企業の法的責任問題に直結します。
2. 損害賠償と信用の失墜
権利侵害が発生した場合、企業は権利者から損害賠償や差止請求を受ける可能性があります。実際に、海外では生成AIによる著作権侵害を認める判例も出てきています。金銭的な損害だけでなく、法律を遵守しない企業としてのレッテルは、顧客や取引先からの信用を大きく損ないます。
3. 世界的な法整備の潮流
2025年9月に日本で「AI法」が全面施行されるなど、AIの利活用に関するルール作りは世界的な潮流です。現時点では事業者の努力義務を促す内容が中心ですが、今後、より厳しい規制が導入される可能性も十分に考えられます。国内外の法律の動向を常に注視し、先んじて対策を講じることが重要です。
関連記事:【AI新法を徹底解説】企業が知るべき日本の新ルールと対策
【法律①:著作権法】生成と学習における2つの論点
生成AIと著作権法の関係は、最も複雑で議論の的となっている法律問題です。論点は、AIがコンテンツを「学習する段階(インプット)」と「生成する段階(アウトプット)」の2つに大別されます。
1. 学習段階(インプット)の論点
日本の著作権法第30条の4では、原則として、著作権者の許諾なくAIの学習用データとして著作物を利用できると解釈されています。ただし、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とされています。例えば、有料で販売されている学習用データベースを不正にコピーして学習させるような、悪質なケースがこれに該当する可能性があります。
2. 生成段階(アウトプット)の論点
AIが生成したコンテンツが著作権侵害となるかは、主に「類似性」(既存の著作物と似ているか)と「依拠性」(既存の著作物を参考にして作られたか)の2点で判断されます。たとえAIが生成したものであっても、特定のキャラクターやイラストに酷似しており、かつユーザーがそれを意図して生成した(依拠性がある)と判断されれば、著作権侵害となる可能性が高まります。
企業が取るべき著作権対策
- ガイドライン策定: 特定のアーティストの画風を模倣するようなプロンプトを禁止するなど、従業員向けの利用ガイドラインを定めます。
- 生成物のレビュー: AIが生成したコンテンツは、公開前に必ず既存の著作物と酷似していないか、人間の目でチェックする体制を構築します。
- ツールの規約確認: 著作権侵害のリスクに関して、補償や免責を約束している法人向けサービスを選定することも一案です。
関連記事:【生成AIと著作権】知らないと怖い!安全に使うための知識とリスク対策
【法律②:個人情報保護法】AI利用で注意すべきこと
顧客情報や従業員情報といった個人情報の取り扱いは、生成AI利用における最大の法律リスクの一つです。特に外部のクラウド型AIサービスを利用する際は、個人情報保護法への抵触に細心の注意が必要です。
1. 個人情報の「入力」は「第三者提供」か?
従業員が、顧客の氏名や連絡先を含む問い合わせメールを、社外の生成AIサービスに要約目的で入力するケースを考えてみましょう。この行為は、本人の同意なく個人情報をサービス提供事業者(第三者)に渡す「第三者提供」に該当し、法律違反となる可能性があります。
2. 安全管理措置義務の遵守
企業は、取り扱う個人データを安全に管理するための措置を講じる義務があります。生成AIの利用においては、「機密情報や個人情報は原則として入力しない」というルールを策定し、従業員に徹底させることが、この安全管理措置の根幹となります。
3. 企業が取るべき個人情報保護対策
- 法人向けサービスの利用: 入力したデータがAIの学習に再利用されないと明記している、セキュリティレベルの高い法人向けプランを選択します。
- 従業員教育: 何が個人情報にあたるのか、なぜそれをAIに入力してはいけないのか、という基本的なリテラシー教育を定期的に実施します。
- 匿名化処理: どうしてもAIで分析したい場合は、個人を特定できないようにデータを加工(匿名化)してから入力するプロセスを構築します。
関連記事:【生成AIと個人情報】企業が守るべき法律と安全対策を解説
| 法律分野 | 主な法律リスク | 企業の基本対策 |
| 著作権法 | AI生成物が既存の著作物と酷似し、権利侵害となる。 | ・類似性をチェックするレビュー体制の構築 ・社内ガイドラインの策定 |
| 個人情報保護法 | 従業員が個人情報をAIに入力し、情報漏洩や目的外利用となる。 | ・原則として個人情報の入力を禁止 ・法人向けセキュアなサービスの利用 |
【法律③:契約・賠償責任】AIが生んだ損害は誰の責任?
「AIが生成した誤った情報に基づいて顧客に損害を与えてしまった」「AIが書いたコードに脆弱性があり、サイバー攻撃を受けた」。このような場合、その損害賠償責任は誰が負うのでしょうか。
AI提供者の利用規約(免責条項)
多くの生成AIサービスの利用規約には、「提供する情報の正確性を保証せず、その利用によって生じたいかなる損害についても責任を負わない」といった趣旨の免責条項が含まれています。つまり、基本的にはAIが生成したアウトプットの責任は、AI開発者ではなく、それを利用したユーザー側にあるというのが現在の一般的な考え方です。
企業(利用者)が負うべき責任
上記の理由から、生成AIの出力をビジネスで利用する場合、その内容の最終的な正しさや適切性を検証し、結果に対する責任を負うのは、利用者である企業自身となります。AIはあくまで「優秀なアシスタント」であり、最終的な「意思決定者」は人間であるという原則を忘れてはなりません。
AIガバナンスの重要性
これらの責任問題に対応するためには、企業内に「AIガバナンス」の体制を構築することが不可欠です。AIの利用に関する方針やルールを定め、リスクを管理し、何か問題が起きた際の対応プロセスを明確にしておくことが、企業としての説明責任を果たす上で重要になります。
生成AIと法律に関する企業の対応策チェックリスト
自社の法務リスク対策が十分かを確認するための、簡易的なチェックリストです。
| チェック項目 | 対応状況(例) | 担当部署の例 |
| 1. 生成AI利用ガイドラインは策定されているか? | 検討中 | 法務、情報システム |
| 2. 従業員への法務・倫理研修は実施されているか? | 未対応 | 人事、法務 |
| 3. 利用するAIサービスの利用規約(特に商用利用、データ取扱)は確認済みか? | 対応済 | 法務、開発部門 |
| 4. 個人情報・機密情報の入力禁止ルールは周知徹底されているか? | 対応済 | 全部門 |
| 5. AI生成物の著作権・ファクトチェック体制は構築されているか? | 検討中 | 事業部門、広報 |
まとめ
本記事では、生成AIのビジネス利用に伴う「法律」の問題、特に著作権法と個人情報保護法に焦点を当てて解説しました。
現時点ではAIに特化した法律が整備途上にあるからといって、無法地帯というわけでは決してありません。既存の法律が生成AIの利用にも適用され、企業はそれを遵守する責任を負います。
法律リスクを過度に恐れてAIの活用をためらうのは得策ではありません。むしろ、本記事で示したような法律の論点を正しく理解し、ガイドラインの策定や従業員教育といった対策をプロアクティブに講じること。その「責任あるAI活用」の姿勢こそが、企業の信頼性を高め、持続的な成長を支える基盤となるでしょう。