【生成AIパスポート】合格ラインは80%?合格率と試験概要を解説
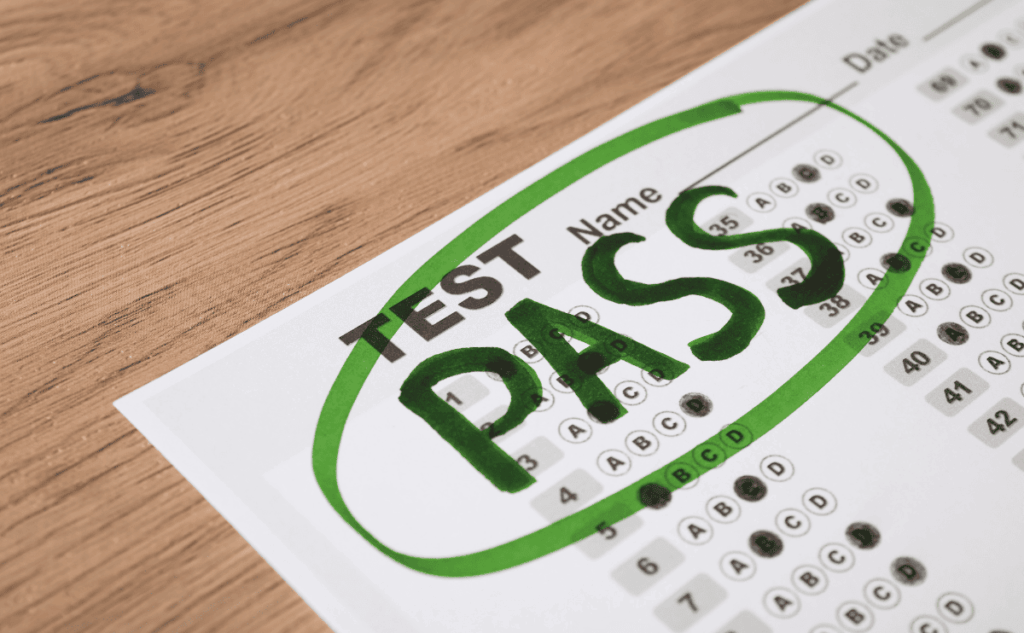
生成AIのスキルを客観的に証明する資格として注目を集める「生成AIパスポート」。これから受験を考えるビジネスパーソンにとって、最も気になるのが「何割取れば合格できるのか?」という合格ラインでしょう。
本記事では、生成AIパスポートの合格ライン、合格率、そして試験の難易度について、最新の情報を基に分かりやすく解説します。
目次
「生成AIパスポート」とは?
生成AIパスポート(Generative AI Passport)は、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する民間資格試験です。
その目的は、AIの基本原理や生成AIの仕組み、活用方法、さらには倫理的な問題や法律(リスク)に関する知識を体系的に習得し、生成AIを安全かつ効果的に活用できる人材を育成することにあります。プログラミングや数学といった専門知識ではなく、ビジネスの現場で「使いこなす」ための実践的な知識が問われます。
関連記事:【必須スキル】生成AIパスポートとは?取得メリットとビジネス活用への道
結論:「合格ライン」は非公開だが「80%」が目安
まず結論から言うと、生成AIパスポートを主催する一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)は、「合否に関する基準点や採点の詳細については開示しておりません」と公式に発表しています。
つまり、正確な合格ラインは非公開です。
なぜ「70%」や「80%」と言われるのか?
では、なぜ多くの情報サイトで「70%」や「80%」といった具体的な数値が語られているのでしょうか。これらは、過去の受験者の自己採点レポートや、試験対策スクールの分析に基づく「推定値」です。
- 70%説: 他の多くのIT系資格が7割を合格ラインとしていることから類推。
- 80%説: 受験者のSNS報告などで「75%で不合格だった」「78%で合格した」といった声が散見されるため、より安全なラインとして80%が目安とされています。
【結論】
公式な合格ラインは非公開ですが、過去の受験者の傾向から、練習問題で常に80%以上を安定して取れるように勉強を進めるのが、最も確実な合格戦略と言えるでしょう。
合格率と難易度:初心者でも合格しやすい?
合格ラインと合わせて気になるのが、試験の難易度です。データを見ると、生成AIパスポートは初心者にも門戸が開かれた、挑戦しやすい試験であることがわかります。
合格率は約75%と高水準
GUGAが公表している過去の試験結果を見ると、合格率は毎回およそ73%〜78%の間で推移しており、非常に高い水準を維持しています。
受験者の多くが非エンジニアやAI初心者であることを踏まえると、しっかりと対策をすれば十分に合格が狙える試験と言えます。
難易度の位置づけ:「ITパスポート」と同等か、やや易しい
AI関連の資格には専門知識を問う難関なものもありますが、生成AIパスポートは、ITSS(ITスキル標準)でレベル1〜2に位置付けられています。
これは、IT系資格の登竜門である「ITパスポート(ITSSレベル1)」と同等レベルです。しかし、ITパスポートがIT全般(ネットワーク、データベース、法務など)の幅広い知識を問うのに対し、生成AIパスポートは「AIの活用」という領域に特化しています。そのため、ITの専門的な知識がなくても、AIに興味があれば学習しやすく、「ITパスポートより易しい」と感じる人も多いようです。
関連記事:【合格率約75%】生成AIパスポートの難易度を徹底解説
必要な勉強時間
合格者からは「10〜20時間程度の勉強で合格できた」という声が多く聞かれます。AIの知識が全くない初学者の方でも、週末や平日の夜を使って、数週間集中して勉強すれば十分に合格圏内に入ることが可能です。
生成AIパスポート試験の概要
| 項目 | 内容 |
| 主催団体 | 一般社団法人生成AI活用普及協会 (GUGA) |
| 試験時間 | 60分 |
| 問題数 | 60問 |
| 形式 | CBT(IBT)方式 ※インターネット経由でのオンライン受験 |
| 出題形式 | 四肢択一式 |
| 受験料 | 11,000円(税込) ※学割 5,500円(税込) |
| 公式の合格基準 | 非公開 |
| 推定合格ライン | 70%〜80%の正答率(80%以上が安全圏) |
| 合格率 | 約75%前後 |
合格の鍵を握る「出題範囲(シラバス)」
合格ラインを目指す上で、どこを重点的に勉強すべきか。その答えはシラバス(出題範囲)にあります。シラバスは大きく5つの章で構成されています。
第1章:AI(人工知能)
AIの定義、歴史、AIの種類(特化型・汎用型など)、シンギュラリティ(技術的特異点)といった、AIに関する最も基本的な知識が問われます。
関連記事:【生成AIの歴史】技術の進化が一目でわかる年表と解説
第2章:生成AI(ジェネレーティブAI)
生成AIの定義、ChatGPTの仕組み、基盤となるLLM(大規模言語モデル)の概要、RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)といった、生成AIの核となる技術概念を学びます。
関連記事:【初心者向け】生成AIとは?仕組み・種類・無料ツール・活用事例を解説
第3章:現在の生成AIの動向
テキスト生成AIだけでなく、画像生成、動画生成、音声生成など、現在どのようなAIサービスが存在し、何ができるのか。また、ディープフェイクのような技術的な動向についても問われます。
第4章:情報リテラシー・基本理念とAI社会原則
(最重要項目の一つ) 生成AIを安全に使うためのリスクについて学びます。個人情報保護、著作権、セキュリティ(プロンプトインジェクションなど)、AIのバイアス(偏見)といった、ビジネスで利用する上で必須となるリスク管理の知識がここに含まれます。
関連記事:【生成AIのセキュリティ】企業が知るべきリスクと対策を徹底解説
第5章:テキスト生成AIのプロンプト制作と実例
(最重要項目の一つ) 生成AIの能力を最大限に引き出すための「プロンプトエンジニアリング」の基礎を学びます。「指示(Instruction)」「コンテキスト(Context)」「役割(Role)」といったプロンプトの基本構造や、優れたプロンプトの実践例が問われます。
効率的な勉強方法とリソース
短期間で合格ラインを超えるためには、効率的な学習が不可欠です。
1. 公式テキストブックを徹底的に読み込む
まずはGUGAが認定する公式テキストを一読し、試験の全体像と主要なキーワードを把握します。出題はシラバスに準拠するため、公式テキストが学習の基本となります。
2. 公式問題集(または対策アプリ)を繰り返し解く
知識をインプットした後は、公式の問題集や、各社が提供する試験対策アプリを使って、ひたすらアウトプットの練習をします。60分で60問を解くため、1問1分のペース配分に慣れることも重要です。
3. 「第4章(リスク)」と「第5章(プロンプト)」を重点的に
合格率が高いとはいえ、AIの専門用語に慣れていないと戸惑うこともあります。特に、合否を分けるのは実践的な内容である「第4章:情報リテラシー・リスク」と「第5章:プロンプト制作」です。この2つの章を重点的に復習し、確実に得点できるようにすることが、合格ラインを超えるための最短ルートです。
関連記事:【保存版】生成AIパスポートの勉強方法を徹底解説!効率的な学習で合格を掴む
まとめ
本記事では、生成AIパスポートの合格ラインと難易度、試験概要について詳細に解説しました。
- 公式の合格ラインは非公開ですが、多くの受験者の動向から80%以上の正答率を目標にすることが安全策です。
- 合格率は約75%と高く、難易度はIT系入門レベル(ITパスポートと同等か、それ以下)とされています。
- 短期間(10〜20時間)の集中学習でも合格は十分可能で、特に「リスク管理」と「プロンプト技術」の分野が重要です。
生成AIパスポートは、これからのビジネスパーソンにとって必須の「AIリテラシー」を証明するための第一歩として最適な資格です。合格ラインの目安を正しく理解し、効率的な学習でぜひ合格を掴み取ってください。





